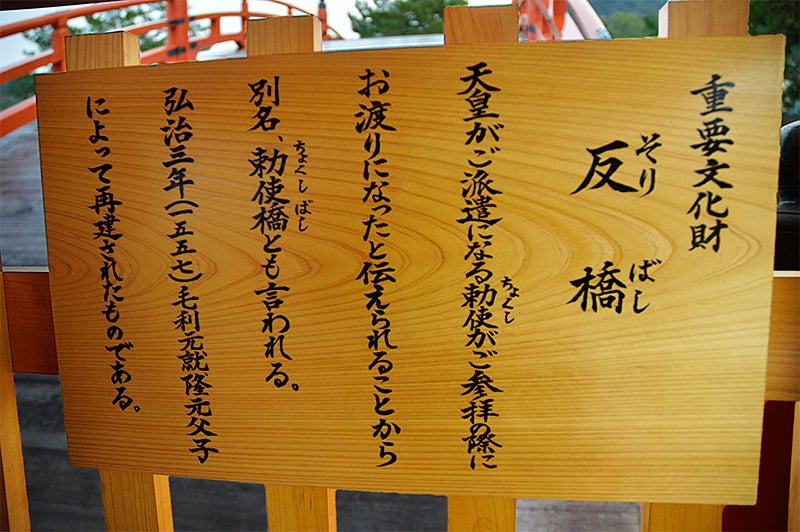海と島を繋ぐ大鳥居・厳島神社〜初冬厳島行(6)←(承前)
宝物館の横から大聖院へと続く中西小路を進みます。
薄暗い時刻に上陸し、そのまま海辺の厳島神社と大願寺、大鳥居から宝物館へと巡っていましたから気付きませんでしたけれど、思っていたよりかなり紅葉が残っていました。
![]()
水が流れているのは白糸川です。
一見かわいらしい流れですが、2005年9月6日の台風14号によって、この川の上流に大規模な土石流が発生し、弥山登山道で表参道となる大聖院コース、その途上に建つ瀧不動堂や瀧宮神社、麓の大聖院境内の一部、滝小路、そしてこの中西小路など、流域を次々と破壊して埋没させたとのことです。
![]()
朱い欄干の滝橋。
ちなみに2005年9月の台風で、この滝橋は↓こんなことになってしまっていたようです(泣)
![]()
大量の流木により閉塞した滝橋(1)
土砂災害ポータルひろしま/写真で見る広島県の砂防/白糸川被災復旧写真集
![]()
欄干に「たきばし」との銘板。
この滝橋を渡ると、厳島神社の本殿真裏にある筋違(すじかい)橋から続く滝小路に入って、大聖院の正面へと至ります。
ここから弥山の頂上近くまで、この白糸川に沿いながら登拝して行くことになります。
![]()
厳島神社の別当寺であった多喜山大聖院水精寺(たきやま だいしょういん すいしょうじ)の仁王門。
大聖院
山号:多喜山(滝山)
宗派:真言宗御室派大本山
本尊:十一面観音(観音堂)
・・・波切不動明王(勅願堂)
創建:806年(大同元年)伝
開基:空海伝
札所:中国三十三観音14番
・・・山陽花の寺1番
・・・広島新四国八十八ヶ所霊場87番
宮島弥山 大本山 大聖院ホームページ
宮島観光協会/観光スポット/大聖院
宮島観光公式サイト/大聖院
しかし今回は時間の都合によって、この大聖院本坊への参拝は泣く泣く割愛させて頂きました。
本坊には観音堂、摩尼殿、勅願堂、八角万福堂、大師堂、遍照窟、施無畏堂、愛染堂、薬師堂、阿弥陀堂などの堂宇が建ち並びます。
仏像も、下に↓引用させて頂きますように、大願寺〜初冬厳島行(5)でご紹介させて頂いた十一面観音をはじめ、
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
宮島弥山 大本山 大聖院ホームページ/仏像
波切不動明王、阿弥陀如来、金剛界曼荼羅、胎蔵界曼荼羅、賓頭盧尊者、十六善神、三十六童子、百体不動と千体不動、仏庭―如宛、水掛地蔵尊と修行大師、愛染明王、薬師如来と十二神将、釈迦涅槃像と十六羅漢、三十三変化観音、読み書きそろばん地蔵、十二支地蔵、水子地蔵、六波羅密地蔵、一願大師、稚児大師、子育て観音、普陀山招来十一面観音像、百観音お砂踏み、目出しダルマ、狸僧、かえる観音など多彩を極めます。
また、本堂観音堂には砂マンダラもあり、地下には中国三十三観音霊場お砂踏み道場としての戒壇めぐりができます。
ということで、この本坊を本気で隅々まで参拝させて頂くと、ほぼ半日がかりとなってしまうことは前回すでに実証済みでしたから、私たちは仁王門の前にて静かに合掌し一礼すると、3つある登山ルートのひとつ、大聖院コースへと進みました。
![]()
宮島観光公式サイト/弥山散策/全体マップ
ただ、弥山が大聖院にとってもご本尊のようなものであり、また境内地でもありますから、山頂の弥山本堂、三鬼堂、不消霊火堂、大日堂、観音堂、文殊堂などへはお参りをさせて頂きますので、大聖院への参拝を全て完全に割愛した、というわけではありません。
むしろ肝心要のホットスポットへのみ集中し、お参りをさせて頂いたという解釈も可能かと思われます(苦笑)
![]()
大聖院(だいしょういん)
・江戸時代、厳島神社の運営を行う別当職(べっとうしょく)の役割を果たし、十数ヶ寺あった社僧(しゃそう)を率いて法会(ほうえ)や延年(えんねん)・晦日山伏(みそかやまぶし)など行っていた。
・天正12(1584)年仁和寺(にんなじ)の任助法親王(にんじょほうしんのう)の滞在があり、以来仁和寺との関係を深め、現在は真言宗御室派(しんごんしゅうみむろは)の大本山になっている。また16世紀後半にはここで豊臣秀吉(とよとみひでよし)が和歌の会を行った。
・代々の別当職は座主(ざす)と称され、その起源は12世紀高倉上皇(たかくらじょうこう)と平清盛(たいらのきよもり)などの参詣を記した「高倉院厳島御幸記(たかくらいんいつくしまごこうき)」に記されている座主とされている。
![]()
整備された白糸川。
左に見えている鳥居をくぐって進みます。
![]()
瀬戸内海国立公園(宮島)の案内地図看板。
厳島は島自身がご神体であり、弥山はもちろんご神体山となりますので、私は長い間、決められた登山道以外は全て禁足地かと思っていましたけれど、実の所そのような決まりはないようです。
だからといって、好き勝手に歩き回るのは不敬でしょうし、何より危険です。
遭難者も、年に何人かはいるそうですし。
さらに厳島は「植物の正倉院」と呼ばれるほど、その森林は多様性に富んで古来の姿を遺しているとのことですから、貴重な自然を守るためにも、無闇に森の中へと分け入ることは厳に謹むべきですね。
厳島での登山については、こちらで詳しくご紹介されていますので、ご参照ください。
宮島弥山倶楽部
![]()
今一度、白糸川の同じ風景を広くヨコ位置で見てみます。
2005年の台風によって、ここは土石流に流された巨岩により埋め尽くされていたようです。
![]()
渓流保全工(大聖院下流付近 その3)被災全景
![]()
渓流保全工(大聖院下流付近 その3)渓流保全工完成パース
![]()
渓流保全工(大聖院下流付近 その3)渓流保全工完成写真
土砂災害ポータルひろしま/写真で見る広島県の砂防/白糸川被災復旧写真集
そして2008年10月、被災から丸3年を経てこのように復旧工事が完了し、通行止めになっていた大聖院コースも開通となりました。
復旧工事の様子は、↓こちらにも分かりやすく掲載されていますので、ご参照ください。
「みせん」第34号E・瀬戸内海国立公園宮島地区パークボランティアの会
私が前回はじめて厳島へ訪れたのも同じ2008年でしたが、残念ながら2月でしたので、この大聖院コースへは未だ立ち入り出来ないままでした。orz
![]()
白糸川の向こうには、大聖院本坊の堂宇が望めます。
一番手前が霊宝館、その右に黒瓦の切妻屋根が客殿、左の切妻屋根が観音堂、さらに観音堂の向こうに見える宝珠の屋根が摩尼殿、かと思われます。
![]()
大聖院コースの入口となる鳥居。
ここからようやく、弥山への登拝が始まりました。
残った紅葉が、鮮やかに参入口を彩ります。
左に見えている立派な石垣と漆喰塗りの土塀は、かつて西方院という大聖院の僧坊とその庭園で、今は「雪舟園」として遺されているそうです。
ここには「西方院跡」と書かれた石碑と「雪舟園」と書かれた門があります。この門の中は、今は私有地になっていて入ることはできませんが、昔は、隣りにある大聖院の宿坊だった「西方院」というお寺と庭園があったところです。その庭園は、涙で描いたねずみの伝説で有名な雪舟が造ったという言い伝えがあるそうです。
Hirolin's weBlog・・・瀬戸内CRUISING/西方院(雪舟園)跡(宮島)
![]()
鳥居の前にある石碑やお地蔵さま。
上で見た災害時の写真にはありませんので、流され堆積した岩々や土砂の中から見つけ出され、ここに戻されたものとおもわれます。
このような作業も地道に積み重ねられたことで、大聖院コースが復旧されたのかと実感されます。
![]()
鳥居をくぐると、左手に懺悔(さんげ)地蔵の祠があります。
![]()
懺悔地蔵
貪りの心、怒りの心、愚痴の心、この三つの煩悩によって、肉体と、言葉と、心の上につくさまざまの悪業の一切を包みかくすことなく懺悔いたします。
一切を懺悔することは、信仰の第一歩であり、さまざまの罪障を消滅する功徳であります。ここに懺悔し終わって、今後ひたすら善業を行いお誓い下さい。
Wikipedia/懺悔/仏教における懺悔
仏教において懺悔(さんげ)とは、自分の過去の罪悪を仏、菩薩、師の御前にて告白し、悔い改めること。
(中略)
懺悔文という偈文があるほか、山岳修験では登山の際に「懺悔、懺悔、六根清浄」と唱える。
ということで、この鳥居から先、弥山を登拝するにあたっては、ちゃんと懺悔してから進みなさいね、とのお教えです。
私たちはここで、懺悔文と般若心経、お地蔵さまのご真言などお唱えしました。
懺悔文(さんげもん)
我昔所造諸悪業・我れ昔(むかし)より造る所のもろもろの悪業(あくごう)は
皆由無始貪瞋癡・皆無始(むし)の貪瞋癡(とんじんち)に由(よ)る、
従身語意之所生・身語意(しんごい)より生ずる所なり、
一切我今皆懺悔・一切我今(いっさいわれいま)、みな懺悔(さんげ)したてまつる
私が昔から作ってきた色々な悪い業は、
遠い過去から積み上げてきた、貪瞋癡すなわち三毒によるものです。
それは、体で行った・話した・思ったという三業から生まれたのです。
私は今、それら全てを懺悔します。
Wikipedia/懺悔偈
![]()
お参りを終えて、今一度お地蔵さまの祠へ見入ります。
と、サチエがペロッと舌を出しました〜!?
どうやら、舌を抜かれていないかどうか、気になったようです(苦笑)
もちろんこちらは閻魔さまではありませんので、それはない筈なのですが、自分の懺悔に自信がなかったようです…
ちなみに、まったくの余談ですが、鳥居≒門ということと、閻魔≒地獄で思い出されるのが、ダンテ『神曲』地獄篇第3歌に登場する「地獄の門」に記された銘文ですね。
我を過ぐれば憂ひの都あり、
我を過ぐれば永遠の苦患あり、
我を過ぐれば滅亡の民あり
義は尊きわが造り主を動かし、
聖なる威力、比類なき智慧、
第一の愛、我を造れり
永遠の物のほか物として我よりさきに
造られしはなし、しかしてわれ永遠に立つ、
汝等こゝに入るもの一切の望みを棄てよ
Wikipedia/地獄の門/地獄の門の碑銘
もちろん、この弥山とは、古代インドの聖なる山である須弥山(しゅみせん)、あるいは御山(おやま、みやま)という古来からの呼び名に由来するとのことですから、地獄ではなく天国への山ということかと思われますけれど、何か、覚悟としては似ています(笑)
![]()
ネックウォーマーを口元まで引き上げて、舌を抜かれまいと用心するサチエ。
目つきも胡乱になってます。
紅葉の向こうには、大聖院本坊のお堂群が見えていました。
![]()
ようやくスッキリとした青空になりました。
これから約3kmのこの道を、片道約1時間半~2時間(休憩含む)とされている所、各所参拝もありますので丸3時間もかけて、登っていくととなります(笑)
![]()
石段2000段!古くからの石仏や町石が残っており、展望の良い場所がたくさんあるコースです。道も改修され、危険な場所はありません。途中の里見茶屋跡でほっと一息、目の前の美しい景色をお楽しみください。
宮島観光公式サイト/弥山散策/大聖院コース
![]()
石段を振り返ります。
![]()
前を行くサチエを呼び止めて、巨岩と記念撮影。
厳島は、ひとつの巨大な花崗岩の塊で、それが隆起し今の様相になったとのことで、花崗岩は比較的に風化しやすく、表層から深部へ向け大きく亀裂が発生するため、このような巨岩になるということです。
![]()
きれいに復旧された白糸川。
被災時は↓こんな状態。
![]()
被災全景
土砂災害ポータルひろしま/写真で見る広島県の砂防/白糸川被災復旧写真集
![]()
右手に、大聖院本坊最古の建物で、境内の一番奥に聳える大師堂の屋根が見えています。
![]()
さらに、よく見える位置から撮ってみました。
大師堂の手前右手に建つのは、宮島七福神を祀る八角万福堂です。
このように、大聖院コースと本坊の境内は白糸川を挟み平行していますので、どうせなら大師堂の辺りからこちらへ橋を架けて頂ければ、大聖院本坊をお参りしながら通り抜け、そのまま弥山へ登拝できるのになあ、などと思います。
まあ、それは、モノグサな人間の了見かとは思いますけれど…(苦笑)
![]()
来た方を振り返ると、大野瀬戸が望めました。
大聖院本坊境内の御成門から同じ方向を望むと、さらに絶景が見渡せるとのことです。
![]()
立派な祠のお地蔵さま。
サチエが食い入るように見入っています。
そして手前にある舟形の石像も、お地蔵さんでしょうか。
おそらく、土石流で半分に割れてしまったものが接合されているようです。
![]()
右の柱に「宮嶋新地蔵八拾八ヵ所第三拾壱番札所」と板書されていました。
その「宮嶋新地蔵」をググってみましたけれど、残念ながら詳細は不明のままです。
実はこのお地蔵さん、土石流によって流木が祠を突き破り、その直撃を受けていったん首が取れてしまったとのこと。
今はどこかから拾われて、元に戻されたようですが、首元の割れ目はそのままのようです。
左に見えている変な形の燈籠は、頭と足だけが残っていますが、その間の部分が行方不明のままだそうです。
その他にも、ここには古い町石や石仏群があったそうですが、すべてが土石流により行方不明になってしまったとのこと…
宮島弥山倶楽部/大聖院ルート
(つづく)
~いつも応援ありがとうございます~