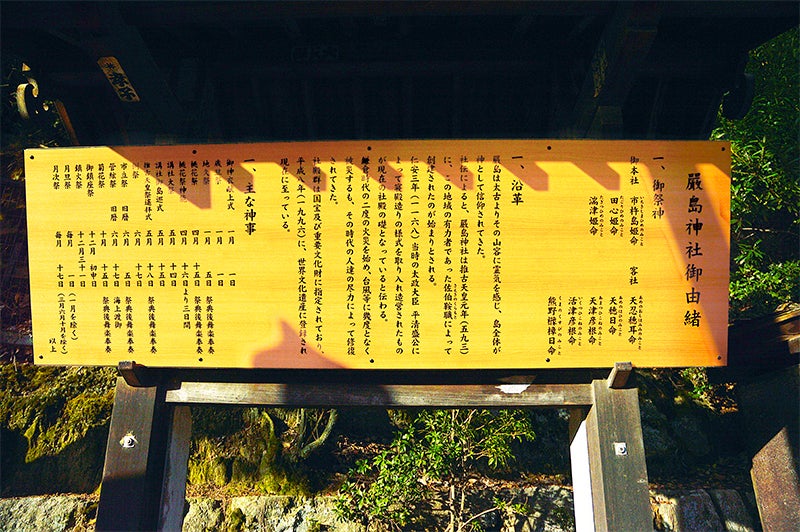幻の宮への扉をひらく斎宮歴史博物館3〜2016冬至伊勢行(13)←(承前)
![]()
斎宮寮復元模型(400分の1)
展示室Ⅱ「ものからわかる斎宮」へ入ると、先ずこの復元模型が迎えてくれます。
発掘でよみがえった斎宮
昭和45年(1970)、現在博物館の建つ古里地区(ふるさとちく)で発掘調査が行われ、長い間埋もれていた斎宮が再びその姿を現しました。昭和54年には、東西約2キロ、南北約700メートル、面積約137ヘクタールが国の史跡(しせき)に指定され、現在も計画的な発掘調査が続けられています。
これまでの調査の結果、斎宮では、奈良時代後期になると史跡東部で、区画道路により碁盤目状に区切られた方格地割(ほうかくちわり)が造営され、建物が整然と建ち並んでいたことが判明しています。この地割は、約120メートル四方の区画が東西7列・南北4列並んで構成されるという大規模なものでした。
斎宮歴史博物館/斎宮の様子
![]()
上の写真の真ん中あたりをアップ。
中央の左側に大きめの建物が密集しているのが寝殿で、ここが斎王の居宅ということです。
その右、道を挟まず隣接するのが配膳を司る采女司(うねめのつかさ)。
そして寝殿の真後ろに神殿、その左隣は寮頭館で右隣が神まつりを司る主神司(かんのつかさ)、さらに右隣が膳部司(かしわでのつかさ)で調理を司りますますから、これらは斎王を中心として斎宮内での神まつりを考慮した配置かと思われます。
また、手前の正面には警備を司る門部司(かどのつかさ)が並んで配置され、斎宮を堅く守っていた様子が伺えます。
![]()
先ほどの逆側から見た斎宮寮復元模型。
斎宮寮復元模型には、斎宮の中を擬似的に歩き回ることができるプログラム「斎宮バーチャル探訪」が楽しめるディスプレイも2台設置されています。
斎宮歴史博物館/常設展案内
とのことなので、模型の向こう側に引っ付いている2つの四角い木の箱がそのディスプレイだと思いますが、その時そのような機能のあることを知りませんでした(泣)
Q 展示室にある400分の1の斎宮の模型で、瓦葺きの建物が全くないのはどうして?
A 斎宮で発掘調査をしていると、ほとんど見つからないのが瓦です。建物を取り壊す時には破損した瓦はたいていその場所に埋めますから、斎宮の建物には瓦が葺かれていなかった、と考えられます。また、平安時代後期に編纂された『新任弁官抄』という文献には、斎宮の内院は檜皮葺き、中院、外院は板葺きや萱葺きとしており、瓦は使われていなかったことは文字記録からも裏付けられています。
斎宮歴史博物館/斎宮Q&A
![]()
展示室Ⅱの全景。
その真ん中に、斎宮跡発掘調査の様子が原寸大で再現されています。
![]()
手前に割れた土器が沢山埋められているのは「土器溜り」。
土器溜まり(どきだまり)
斎宮の中心部である内院と呼ばれる区画では、建物の隅にあたるような場所から土器を大量に棄てた穴や溝がしばしば発見されます。出土するものは、その大半が土師器の杯・皿で、儀式や饗宴に使われたと考えられています。内院地区で出土する土器の90%以上が土師器で、この傾向は平安宮の内裏などとも共通します。
斎宮歴史博物館/Web版斎宮今昔/国史跡斎宮跡(南東部)
その右上は「掘立柱建物の柱穴」、その向こうに長細く掘られている溝が「雨落ち溝」。
さらにその右向こうの穴が、「柵列(さくれつ)の柱穴」。
![]()
発掘作業中の女性パネル前にこんもりと盛り上がった土が、遺跡を覆っていた包含層(ほうがんそう)で、その表面はさらに耕作土などで覆われていたそうです。
左の台形に切り出された地層の上が耕作土で下が包含層を示していますが、その手前にあるモニターの付いた四角い箱は、何か子供向けのゲームみたいなもののようですが、何なのか分かりません…
向こうの壁面にも、椅子があって何かゲーム的なものだったと思いますが、これも記憶に残っていません。orz
![]()
「斎宮ゆかりの史跡」
三重県は旧国でいえば、伊賀・伊勢・志摩・紀伊東部の四ヶ国からなり、南北に長い。
斎宮のある多気郡明和町は県の中央やや南部、伊勢市と松阪市の中間に位置している。
旧伊勢国の南部で、志摩にも近く、伊勢神宮を中心とした地域の西の端にあることがうかがえる。
![]()
羊型硯(ひつじがたすずり)奈良時代
このクルリと輪になった角はアモン角と呼ばれるそうですが、まったく日本的なイメージではありませんね。
羊は羊?
斎宮跡出土の代表的な遺物の一つに「羊形硯」があります。別に写真も公開しているので、ぜひご覧いただきたいのですが、わりあいに印象の強いものですので、ああ、あれか、と思われる方も少なくないのではないでしょうか。
さて、羊の頭の飾りをつけた硯は非常に珍しく、平城京で2例あるほか、全国で5例とない「貴重品」だとされます。こういう動物などをかたどった硯のことを「形象硯」といいますが、割合に多いのは鳥形、それも首の長い水鳥の形をまねたものです。水鳥はまさに池や川に浮いているから、硯にして水を張っても「サマになる」のです。そして古墳時代の鳥形埴輪以来造形としてはずっと好まれているので、硯にもそのデザインが使われるのは納得できます。では、羊はなぜ硯になったのでしょう。
(後略)
斎宮歴史博物館/斎宮百話/第7話
このお話し、かなり面白いのでお奨めですけれど、けっこう長くなりますのでリンク先にてお読みくださいませ〜
![]()
「斎宮の起源」
斎宮跡で斎宮に関係する最も古い遺跡は、七世紀末期、飛鳥時代の終わり頃の柵の跡で、たしかな最古の斎王、大来皇女の頃のものと見られている。
八世紀、奈良時代になると様々な遺物が見られ、斎宮の整備がうかがえるが、規模などはそれほどわかってはいない。
斎宮跡の近くでは、北野遺跡、水池土器製作遺跡など、六世紀から八世紀にかけて土師器を作った工房の跡が数多く確認されており、斎宮との関係が指摘されている。
「見つからない木簡」
斎宮跡は台地の上にある。
斎宮が廃絶して後も、もっぱら畑になっており、今でも水田は少ない。
こういう水にとぼしい土中では、木の札に書かれた文字情報、木簡はほとんど残らないのである。
斎宮木簡の第1号の出土はいつのことだろうか。
![]()
「斎宮を支えた官人たち」
斎宮に仕える斎宮寮の、組織や位が定められたのは、奈良時代の初めごろのことである。
斎宮跡ではこのころから、硯や文字を書いた土器(墨書土器)が見つかるようになる。
器に文字を書く目的はよくわからないが、字の書ける人、つまり官人が増加したことや、彼らの活動の終わりごろには、整然とした区画(方格地割)が作られ、斎宮は安定して運用される組織になったようである。
![]()
円面硯、などなど。
この写真からでは説明書が読めません…
どうか、展示品の写真付き目録を、ホームページか出版物で完備して頂けたらと思います(泣)
![]()
緑釉陶器(りょくゆうとうき) 陰刻花文稜椀(いんこくかもんりょうわん) 平安時代
Q 緑釉陶器について教えて?
A 緑釉陶器とは、釉薬(うわぐすり)に鉛と銅を用いて焼かれ、表面が緑色をした焼き物です。通常の釉薬が1200度で焼かれるのに対し、鉛釉は800度で焼成できることから、日本で最初の施釉陶器には鉛釉が用いられました。奈良時代には唐三彩を模して緑・白・茶色を配した奈良三彩が生産されましたが、平安時代になり越州窯(中国浙江省)系青磁が輸入されるようになると、これを模した単彩の緑釉陶器が生産されるようになりました。緑釉陶器は、当初京都の洛北地域や愛知県の猿投窯で生産され、次第に丹波や近江・東濃地域などへ広がっていきました。斎宮跡からは、各地で生産された緑釉陶器が7000点以上出土しています。美しい色彩と光沢を放つ緑釉陶器は高級品であり、斎宮跡から東日本でも突出した量の緑釉陶器が出土していることは、斎宮がいかに重要で平安文化の栄えた場所であったかを物語っています。
斎宮歴史博物館/斎宮Q&A
![]()
「斎宮の儀式」
斎宮の生活についての具体的な様子は、発掘調査からはほとんどわからない。
しかし、まれに見つかる金銅製品や櫛などの木製品は斎宮の雅びの時代のありさまをしのばせ、地鎮祭のようなまつりに使われたらしい土器などは、記録には出てこない日々の生活の中のまつりや儀式について、新しい情報を提供してくれる。
「文字文化の開花」
墨書土器は平安時代になると更に数が増え、官司の名や縁起のいい文字を記したもののほか、十世紀にはひらかなも現れる。
ひらかなは女手ともいわれるので、斎王の身近に仕えた女性の書いたものと考えられる。
硯も、現代のものに近い形になる一方、陶器の破片を硯とした転用硯なども見られ、使う人が増えていたことがうかがえる。
![]()
「斎宮をめぐる土器の流れ」
平安時代、九世紀になると、斎宮では、緑のうわぐすりをかけた緑釉陶器、溶けた灰を使った灰釉陶器などが見られるようになる。
これらの陶器は、愛知県の猿投窯や京都周辺の窯の製品が多く、生産地と消費地のネットワークが作られていたらしい。
平安時代中頃になると、美濃東部(今の岐阜県)、近江(今の滋賀県)などの緑釉陶器も見られるようになる。
「斎宮寮の建物」
斎宮では地面に残された穴から建物の位置を確定する。
礎石を置かず直接地面に柱を立てていたので、柱穴が残るからである。
また、瓦はほとんど出土せず、屋根に瓦を置いていなかったと見られている。
これらは当時の役所の建物としては異例なことで、伝統的な住居建築に近い形だったと考えられている。
![]()
歩いてきた方を振り返ります。
…というのはウソで、実は順路の逆に時計回り=右回りで見ていました(苦笑)
もちろん、このご紹介では順路通りに写真を並べかえていますけれど、この逆回り、よくやってしまいます。
それは、いつもあまり考えないまま、どこでも右回りで巡ろうとするクセがあるからですね。
右繞(うにょう=みぎめぐり)の礼、ということもありますので…
![]()
『幻の宮・発掘』
解説映像(約6分)とのことですが、残念ながら見る余裕がありませんでした。
そのモニター手前には、映像と連動した発掘調査区模型(20分の1)ということで、多分ですけれど、映像で映される位置に、いま見えている小さな人たちが歩いて移動するんじゃないかと思います。
次の機会には、ぜひ拝見したいと思います。
![]()
正面の上段に並ぶ3つの大きな陶器は灰釉陶器。
灰釉陶器(かいゆうとうき)
平安時代初期に愛知県の猿投窯で生産が開始された高火度施釉陶器。釉薬に植物灰を用いており、淡緑色に発色する。椀・皿を主な器形とし、それまでの須恵器に替わって、日常什器として使用された。
斎宮歴史博物館/斎宮関連用語集
手前下の透明ケースに収められているものは、初期貿易陶磁ということです。
この写真では読みにくい説明書ですが、何とか青磁と白磁の文字が読めました。
貿易陶磁器(ぼうえきとうじき)
国外で生産され、わが国に輸入や貢納などによりもたらされた陶磁器。特にわが国で磁器が生産されるのは17世紀以降のことであり、それまではすべて中国・朝鮮からもたらされている。奈良・平安時代にはその輸入量も僅少で、硬く質の高い磁器は緑釉陶器にもまさる高級品だった。斎宮跡からの出土で確実なものは9世紀から10世紀の白磁までさかのぼり、10世紀から11世紀の越州窯系青磁や11世紀~12世紀の北宋系の白磁などとともに、都城や、当時の貿易の玄関口である九州北部を除き、突出した出土量を誇っている。
斎宮歴史博物館/斎宮関連用語集
斎宮にゃいなかった・・・かにゃ
(前略)
平安時代には遣唐使の廃絶により大陸との交流が途絶え、一種の鎖国のような状況下で日本独自の貴族文化が栄えた、というのは、これまでの歴史・国文学界の共通理解でした。ところが近年、歴史学の方からは、遣唐使が廃絶して以降、むしろ大陸との交易が盛んになっていたことが大阪大学の山内晋次氏に代表される研究で、歴史学の側からは次第に明らかにされてきました。
(中略)
斎宮跡の出土資料で、貴重品、といえば緑釉陶器がよく知られていますが、それより高級な貿易陶磁と称される、青磁や白磁の破片もまた出土するのです。河添氏によると、斎宮女御の父親である重明親王の日記『吏部王記』の天暦5年(951)6月9日条には、宮中で「秘色」とよばれる越州窯青磁が使われていた記録があります。同じ時代を生きた斎宮女御なども、あるいは青磁を使っていたのかもしれません。
(後略)
斎宮歴史博物館/斎宮千話一話/第3話
![]()
灰釉陶器(かいゆうとうき)平安時代
これまで見てきた土器に比べたら、かなり凝った造りになっています。
![]()
墨書土器「目代」(平安時代)
高台の中に「目代」と墨で書かれています。
目代(もくだい)とは、日本の平安時代中期から鎌倉期に、遙任国司が現地に私的な代官派遣した家人などの代理人のことである。
Wikipedia/目代
![]()
神都名勝誌(しんとめいしょうし)(長元託宣之図(ちょうげんたくせんのず))
これって有名な、長元託宣事件のことでしょうね?
とすれば、この絵の女性は斎王の嫥子女王で、畏まってその託宣を受けているのが斎宮寮頭の藤原相通、ということになりますね。
1016年、嫥子(せんし・よしこ)女王は斎王に卜定され、1018年に伊勢へ群行しました。
そして1031年(長元4年)、嫥子女王は自らを伊勢神宮の荒魂と称し託宣を下してしまいます。
この時、斎王は酒乱状態のまま、斎宮寮頭であった藤原相通夫妻の不正を糾弾し、朝廷の斎宮軽視を天皇の失政であると非難して、これが斎王託宣事件と呼ばれます。
Wikipedia/嫥子女王
神がかりして託宣を下した斎王
平安時代の斎王 嫥子女王(よしこじょおう)
村上天皇の皇子・具平親王の娘で、後一条天皇の斎宮として12歳で卜定され、32歳で任を解かれるまでの21年間の長きにわたって斎王の位にありました。
長元4年(1031)、月次祭に出席した嫥子女王は、折からの暴風雨の中でにわかに神がかりし、自分は皇大神宮(内宮)第一の別宮荒祭宮(あらまつりのみや)であると叫び、続いて斎宮寮頭夫妻やその家来たちが悪事をはたらいていることや政治の乱れなどを激しい調子で告発する託宣を下したと記録されています。
嫥子女王はこの時27歳。真実、神が斎王の身を借りて託宣したのか、長年生まれ育った都を離れていた憂鬱が爆発したのかはさだかではありません。あるいは漢詩文の才に秀でていた具平親王の血を引いた嫥子女王が、狂気を装って不正を告発したのだとも考えられます。
そののち、後一条天皇の崩御によって帰京し、47歳で藤原教通と結婚。77歳の長寿で亡くなりました。
明和町観光サイト/斎王紹介その4
![]()
青磁椀、だと思います。
![]()
「中世斎宮の変容」
平安時代後期は、斎王制度が次第に衰退する時。
この時期の斎宮の様子は、発掘からまだあまり分かっていない。
建物は数が少なくなり、規模も小さくなっていたようである。
造物としては、この時代の高級な焼き物である青磁や白磁のほか、山茶碗とよばれる愛知県産の土器も見られるようになる。
十二世紀後半には十五年にわたる斎王不在の期間があり、この頃に歌人として有名な西行法師が斎宮を訪れ、その衰退のありさまを目にしている。
何事のおわしますをば知らねども
かたじけなさに涙こぼるる
『西行上人集』
![]()
Wikipedia/西行
コラム 歴史の道から探る王朝人の想い(2)
(前略)
西行は斎宮を訪れ、こんな一首を残しています。
いつかまた いつきの宮のいつかれて
しめの御内に ちりをはらはむ
『山家集(さんかしゅう)』
(大意)いつになったら斎王が神に奉仕なされて、 注連のめぐらされた御内に塵を払うことでしょうか
この歌から作歌時期に斎王が斎宮にいなかったことと、斎宮が荒れるほど人の手が入っていなかったことがわかります。
斎宮は斎王がいなければ、女官などの官人も全員都に帰ってしまいます。斎王制度が続いた六六〇年間、斎宮に誰かが常駐したわけではありません。
この歌が作られた時期は文治二年(一一八六)頃と考えられています。この頃は源氏と平家の騒乱が続いており、斎王が斎宮に在任していない期間が一五年余りもありました。西行はおよそ一五年放置された斎宮を訪れ、斎宮の荒れ果てた姿を見、嘆いて歌を詠んだようです。
(後略)
明和町/さいくうあと通信/第15号
「斎宮の落日」
承久三年(一二二一)の承久の乱で京方が敗北してからは、天皇が即位してもすぐに斎王を選べなくなる。
鎌倉時代中頃には、斎王を置かない天皇が現れ、文永九年(一二七二)を最後に、斎王は伊勢に来なくなり、建武元年(一三三四)ごろ、後醍醐天皇の時代に完全に消滅する。
この時期の斎宮の遺跡は農村的になり、特徴のある遺物や遺構はほとんど見られなくなる。
![]()
ひらかな墨書土器(平安〜鎌倉時代)
![]()
中世墓出土遺物(鎌倉時代)
![]()
山茶碗(やまぢゃわん)
愛知県地方において俗に行基焼あるいは藤四郎焼と呼ばれている硬質・無釉の碗、皿類で、高台端に籾殻痕があるため、一部の地域ではもみがら焼とも呼んでいる。山茶碗の名称は山中の古窯跡に廃棄された碗、皿類の不良品が数多く散在しているところから出たものと思われる。《延喜式》にみえる山坏、小坏を指すとみる場合には、白瓷(灰釉陶器)碗・小碗のセットに当たるが、通常、白瓷碗類が11世紀末葉に無釉の民間雑器に転化した白瓷系陶器のことを指している。
コトバンク/世界大百科事典 第2版/山茶碗
![]()
「斎宮発掘マップ」
平成28年度速報展示
斎宮寮庫・下園東区画の出土品
斎宮にあった役所「斎宮寮」で使用する物品や宝物などを貯蔵するための施設が「寮庫」と考えられています。「寮庫」は、方格地割がつくられた当初(今から約1200年前、奈良時代のおわりから平安時代のはじめごろ)、下園東区画の東隣の「西加座北区画」に位置していました。西暦824年に斎宮を一度、度会郡の離宮院(現伊勢市小俣町)へと移転した際、「西加座北区画」の寮庫は放棄されます。
しかし839年に、その離宮院が火災により焼けてしまい、再び多気郡明和町へと斎宮が戻ってくることとなり、その際に新しく寮庫区画として選ばれたのが「下園東区画」であることが、近年の発掘調査と研究により明らかになってきました。
![]()
そうしてようやく、博物館の観覧を終えて外へと出ました。
ちょうど丸一時間かかって11:30ごろです。
目の前に「ふるさと芝生広場」の風景が広がって、ホッと一息。
正午が近いというのに、さすが冬至ですから太陽もかなり低い位置にとどまっています。
次は近くの神服織機殿神社と神麻続機殿神社を巡り、そこから奥伊勢は大紀町の瀧原宮へと進んで、その後は一気に和歌山街道を辿り高見峠を超えて、奈良県桜井市の三輪を目指します。
この日、三輪での日の入りは16:50ですが、標高1,000mを超える金剛山地の方へと陽は沈みますので、それより少しでも早く到着しないと夕陽を遙拝することができません。
いつものことながら、伊勢で朝陽を遙拝し、そのまま太陽を追いかけて元伊勢の桧原神社で夕陽を遙拝することが私たちのテーマとなっていますので、まだ午前中ですが、早くも少し焦ってきました(苦笑)
そこで、行ってみたかった斎王の森などは割愛することとして、急ぎ神服織機殿神社へと向かいます。
(つづく)
~いつも応援ありがとうございます~